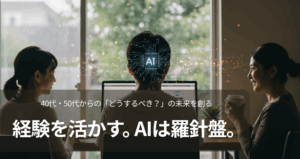AI画像生成はもう怖くない!著作権問題をクリアするAIツールの選び方と活用ガイド
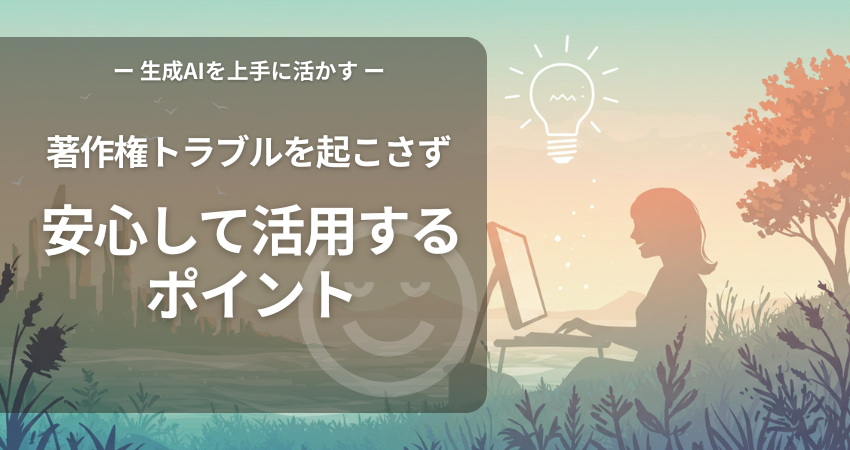
こんにちは!突然ですが、AIで画像を作ってみたことはありますか?
「作った画像をブログやSNSで使ってみたいけど、著作権ってどうなっているんだろう?」
こんな疑問は多くの方が思い浮かぶことと思います。
AI画像生成って聞くと、なんだか専門的で難しそうに感じたり、法律も良くわからなくて作ったとしても不安で使えなかったりしますよね。
でも、実は、いくつかのポイントをおさえておけば、誰でも安心してAI画像生成を楽しむことができるんです。
この記事では、AI画像生成と著作権のモヤモヤをスッキリさせて、安全に楽しくAIツールを使うためのヒントを、一緒に学んでいきましょう!
Contents
この記事を読んでわかること
- AI画像生成と著作権の関係
- 安心して使えるAI画像生成ツールの選び方
- 商用利用ができるAIツールと注意点
- 著作権トラブルを避けるためのコツ
そもそもAI画像生成の著作権はどうなっているの?知っておくべき3つのポイント

「AIが作った画像って、誰のものになるの?」
この疑問、一番気になりますよね。
最初に、AI画像生成と著作権の基本的な考え方について、3つのポイントに分けてお話ししますね。
※AIと著作権について詳しく知りたい方は、文化庁のサイトも参考になります。
参考サイト:AIと著作権について(文化庁)
1. AIが作った画像には、原則として「著作権はない」
まず、これが一番大切なポイントです。
日本の法律では、著作権は「人の思想または感情を創作的に表現したもの」と定義されています。
つまり、人が「こうしたい!」という思いを込めて、工夫して作ったものにしか著作権は認められないんです。
AIは、人間のように「思い」や「感情」を持ってはいません。
私たちが入力した言葉(プロンプト)やデータをもとに、機械的に画像を生成します。
だから、AIが単独で作り出した画像には、原則として著作権は発生しないとされているんですね。
少し意外に感じたかもしれませんね。
でも、これはあくまでも「原則」です。
例外もあるので、次のポイントを見ていきましょう。
2. 人間の「創作的意図」が加われば、著作権が認められることも
AIが作った画像を、私たちがそのまま使うだけなら、著作権は発生しないことが多いです。
でも、もし私たちが「こんな雰囲気の、こんな感じの絵が欲しいな」と、とても細かくAIに指示を出したり、AIが作った画像を元に、さらに手を加えて加工したりした場合はどうでしょうか?
そこには、私たちの「こういうものを作りたい!」という、はっきりとした意図が加わっていますよね。
このような場合は、AIはあくまで「道具」であり、最終的な創作活動を行ったのは私たち自身だと考えられます。
その結果、元の画像に「創作性」があると認められれば、私たちに著作権が発生する可能性があるとされています。
うーん。なんだか少しややこしいですよね。
でも、「AIを道具として使い、自分の思いを込めて作った独創的な画像には著作権があるかもしれない」と覚えておけば大丈夫です。
3. AIに学習させた「元の画像」の著作権は侵害しない?
AI画像生成ツールは、インターネット上のたくさんの画像を学習して、新しい画像を生成します。
ここで心配になるのが、「元の画像を作った人の著作権を侵害していない?」ということですよね。
結論から言うと、多くの国では、AIが学習目的で元の画像を使うことは、著作権の侵害にあたらないと考えられています。
これは、AIが元の画像をそのままコピーして使っているわけではなく、そこから特徴やパターンを学んでいるだけだからです。
ちょうど、私たちが本を読んだり、たくさんの絵を見たりして、新しいアイデアを生み出すのと同じようなイメージです。
でも、注意が必要なのは、AIが元の画像をそのまま複製してしまったり、元の画像の個性を強く反映した画像を生成した場合です。
もし、明らかに「あの作品の絵だ!」とわかるような画像を生成してしまったら、著作権侵害になる可能性も出てきます。
この点が、AI画像生成ツール選びの大きなポイントになってくるんですよ。
安心して使おう!著作権問題に配慮したAIツールの選び方と活用法

AI画像生成ツールはたくさんあって、どれを選べばいいか迷いますよね。
ここでは、著作権問題を気にせず、安心して使えるツールの選び方と、活用する上でのポイントをご紹介します。
1. 利用規約を必ず確認する
これが一番大切なステップです。
それぞれのAIツールには、利用規約(利用ルール)が必ずあります。
そこに、
「生成した画像の著作権はどうなるのか」
「商用利用はできるのか」
「どんな画像なら作っていいのか」
といったことが書いてあります。
「利用規約」と聞くと、なんだか難しそうで、つい読み飛ばしたくなってしまいますよね。
専門用語ばかりで頭が痛くなる…そう思ってしまう気持ち、とてもよくわかります。
でも、実はこの規約こそが、私たちを著作権トラブルから守ってくれる「お守り」のようなものなんです。
最近のツールは、その「お守り」をより理解しやすいように工夫してくれています。
大事なポイントをわかりやすくまとめてあることが多いので、まずは「商用利用」や「著作権」といったキーワードを探してみてくださいね。
2. 商用利用に特化したツールを選ぶ
ブログやSNSで画像を使う予定があるなら、商用利用ができることを前提に作られているツールを選ぶのがおすすめです。
代表的なツールとしては、CanvaやMicrosoft Designerなどがあります。
これらのツールは、生成した画像を商用利用できることが明確にされており、安心してビジネスに活用することができます。
おすすめの画像生成ツール3選|安心して使えるサービスをご紹介

ここでは、特に著作権の心配が少なく、初心者の方でも使いやすいAI画像生成ツールを3つご紹介します。
ただし、それぞれに条件等ありますので商用利用する際は必ず利用規約を確認してくださいね。
1.Canva
- 特徴
デザインツールとしておなじみのCanvaにも、AI画像生成機能が搭載されています。
使い方はとても簡単で、文字を入力するだけで、Canvaのデザインに合ったおしゃれな画像が作れます。
生成した画像は、Canvaの利用規約の範囲内で、商用利用も可能です。 - 価格
無料プランでも利用できますが、有料プラン(Canva Proなど)だとより多くの機能が使えます。 - おすすめポイント
いつものデザインツールの中で完結できるので、ブログやSNSの画像作成に便利。
著作権の心配が少ないので、初心者でも安心です。 - サイト:Canva(https://www.canva.com/)
2.Microsoft Designer (旧Bing Image Creator)
- 特徴
Microsoftが提供するAI画像生成ツールです。
入力したテキストから、高品質な画像を素早く作ってくれます。
利用規約に基づき、生成された画像は商用利用が可能とされています。 - 価格
無料で利用できます。Microsoftアカウントがあれば、すぐに始められます。 - おすすめポイント
無料なのに非常に高機能で、ユニークな画像をたくさん作ってくれます。
商用利用もできるので、ブログのアイキャッチ画像などにもぴったりです。 - サイト:Microsoft Designer(https://designer.microsoft.com/)
3.ImageFX
- 特徴
Googleが提供するAI画像生成ツールで、シンプルで直感的な操作が魅力です。
キーワードを組み合わせるだけで、さまざまなスタイルの画像を生成できます。
利用規約上、商用利用が可能とされており、安心して使うことができます。 - 価格
無料で利用できます。Googleアカウントがあれば、すぐに試すことができます。 - おすすめポイント
Googleの技術が詰まっていて、とても質の高い画像が生成できます。
インターフェースがシンプルなので、AIツールに慣れていない方でも、気軽に始められますよ。 - サイト:ImageFX(https://labs.google/fx/ja/tools/image-fx)
まとめ|AI画像生成はルールを守れば怖くない!
今回は、AI画像生成の著作権問題について、一緒に見ていきました。
この記事では、AIを楽しく活用したいという想いを込めて、AI画像生成ツールを安心して使うためのヒントをお伝えしました。
著作権の考え方やツールのルールは、社会の変化に合わせて変わっていくことがあります。
僕自身は法律の専門家ではないので、あくまで「今、知っておくと安心なこと」として、利用する側の目線でご紹介しました。
そのため、ご自身のビジネスやブログで使う場合は、必ずご自身の目で最新の利用規約をチェックして、ご自身の判断で利用するようにしてくださいね。
一緒に新しいAIの世界を楽しみながら、一歩ずつ進んでいきましょう!
もし、この記事を読んで「AI画像生成、やってみようかな」と思ってくれたら、とても嬉しいです。