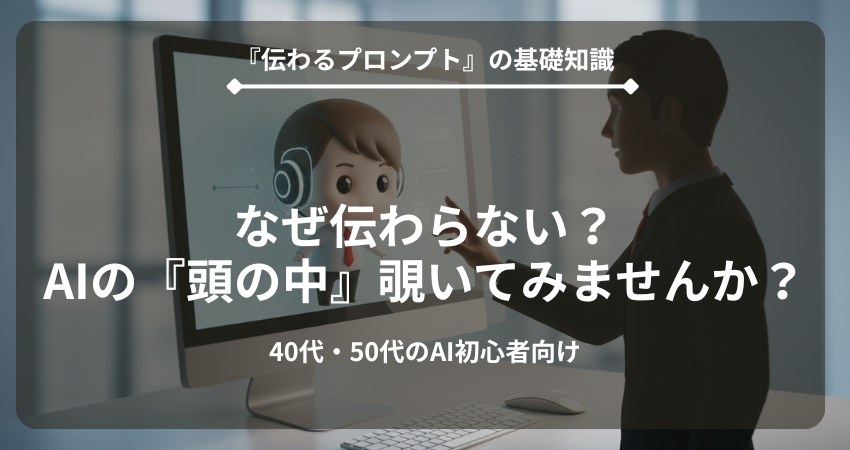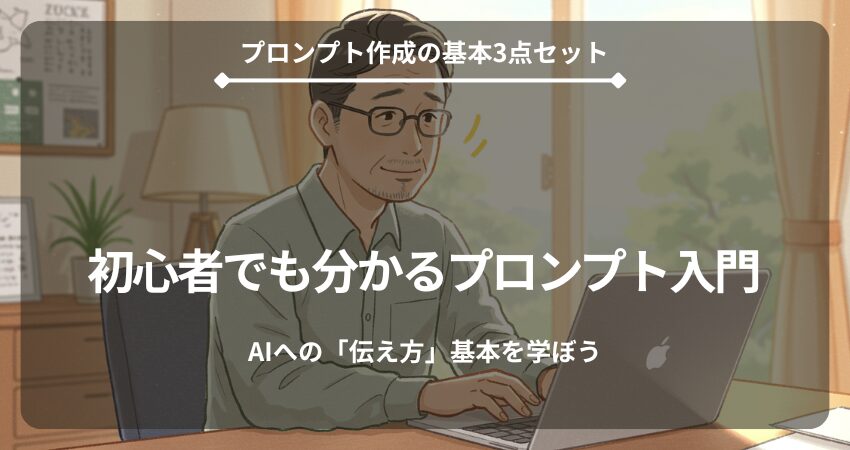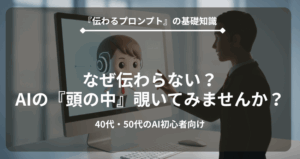AIとの対話力が劇的に向上!今日から使えるプロンプトのコツと実践テクニック
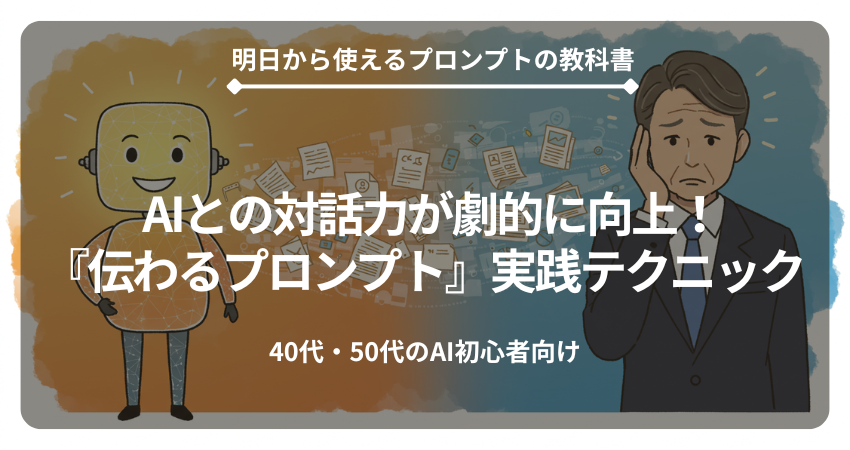
前回の記事「AIは『推測』で答えていた?!なぜAIに意図が伝わらないのか、その理由を徹底解説」では、AIが私たちの言葉をどう理解しているのか、その根本的な仕組みを解説しました。
AIが私たちの意図を完璧に「理解」しているわけではなく、与えられた情報をもとに「推測」で答えを組み立てている、ということがわかったはずです。
でも、知識だけでは何も始まりませんよね。
「AIの仕組みはわかったけど、じゃあ具体的にどうすればいいの?」
「明日からすぐに使えるプロンプトのテクニックが知りたい!」
多くの方がそう感じていると思います。AIとの対話は、まさに練習あるのみ。
正しい知識と、それを実践する勇気があれば、あなたのAI活用は劇的に変わります。
この記事では、前回の理論編で学んだ知識をベースに、AIへの指示が劇的に伝わるようになる具体的なプロンプトのコツを、初心者の方でもすぐに試せるように分かりやすく解説します。
さあ、AIとの対話の扉を一緒に開いていきましょう。
Contents
なぜ「思った通りにならない」のか?5つの主な理由

AIの「頭の中」が少し見えてきましたね。
AIが推測で答えを組み立てている以上、私たちが具体的な情報を与えることが何よりも重要です。
ここでは、プロンプトがうまくいかない5つの主な理由と、その解決策を見ていきましょう。
1. 情報が不足している
よくあるパターン: 「プレゼン資料を作って」
これは、AIが困ってしまうプロンプトの代表例ですね。その理由は以下のポイントが不明だからです。
- テーマは何?
- 対象者は誰?
- どんな構成にする?
- 何ページくらい?
改善プロンプト: 「40代の個人事業主向けに、SNS活用のメリットを5分で説明するプレゼン資料を、5スライド程度で作って」
2. 曖昧な表現が多い
よくあるパターン: 「おしゃれなデザインで」「分かりやすく」「簡潔に」
これは、AIの理解が人によって異なる抽象的な言葉に頼っているため、AIが意図を汲み取れない例です。
AIが困る理由は、以下のポイントが不明確だからです。
- 「おしゃれ」の基準が人によって違う
- 「分かりやすさ」の定義が不明確
- 「簡潔」の程度が分からない
改善例:
- 「おしゃれ」→「モダンで洗練された、白と青を基調とした」
- 「分かりやすく」→「専門用語を使わず、具体例を3つ入れて」
- 「簡潔に」→「各項目3行以内で、全体で300文字程度に」
改善プロンプト:「白と青を基調としたモダンで洗練されたデザインで、専門用語を使わず、具体例を3つ入れて各項目3行以内で表現。全体で300文字程度にまとめて」
3. 前提条件を省略している
よくあるパターン: 「この続きを書いて」(何の続きか不明)
これは、AIに文脈が伝わっておらず、書くべき内容を判断できない例です。
AIが困る理由は、以下のポイントが不明だからです。
- 文脈が分からない
- どんなトーンで書けばいいか分からない
- 長さや構成の指定がない
改善プロンプト: 「上記のブログ記事(40代向けAI活用術)の続きを、同じトーンで500文字程度、具体的な活用例を3つ挙げて書いて」
4. 複数の指示が混在している
よくあるパターン: 「企画書を作って、それと会議資料も作って、あとプレゼンの練習もしたい」
これは、AIに一度に複数のタスクを依頼しており、優先順位や関連性が不明なため、AIが混乱してしまう例です。
AIが困る理由は、以下のポイントが不明だからです。
- どれから手をつけていいか分からない
- それぞれの関連性が不明
- 優先順位が分からない
改善方法: 一つずつ分けて依頼する、または優先順位と関連性を明確にする
5. 期待値の設定が不適切
よくあるパターン: 人間レベルの創造性や判断を期待する
これは、AIの能力範囲を超えた依頼であり、AIが期待された答えを生成できない例です。
AIが困る理由は、以下のポイントがAIに備わっていないからです。
- AIには経験や感情がない
- 創造性には限界がある
- 判断基準を与えられていない
改善方法:AIに感情や個性を求めてしまうと、期待通りの結果は得られません。
例えば、「感動的な文章を作って」ではなく、「読み手が『頑張ろう』と思えるような、前向きで励ましのトーンで書いて」のように
具体的な言葉で感情を表現するよう依頼します。
効果的なプロンプトの基本原則

AIに伝わるプロンプトには、いくつかの「型」があります。これらを意識するだけで、劇的に結果が改善します。
原則1:「5W1H」を意識する
- What(何を): 何を作成・実行したいのか
- Who(誰が・誰に): 対象者は誰か
- When(いつ): 期限や時期の指定
- Where(どこで): 使用場面や環境
- Why(なぜ): 目的や背景
- How(どのように): 方法やスタイル
実例: 「(What)SNS投稿用のアイキャッチ画像を、(Who)40代の個人事業主に向けて、(When)明日の朝投稿予定で、(Where)InstagramとXで使用するために、(Why)AI活用の啓発が目的で、(How)親しみやすい手描き風イラストで作成して」
原則2:具体性を重視する
- 抽象的: 「きれいな画像」
- 具体的: 「清潔感のある白背景に、やわらかい自然光で照らされた」
- 抽象的: 「分かりやすい説明」
- 具体的: 「中学生でも理解できるレベルで、具体例を2つ含めて」
原則3:段階的に指示する
一度に全てを詰め込むより、段階的に依頼した方が正確な結果を得られます。
- 第1段階: 「40代向けのAI活用ブログ記事の構成案を作って」
- ↓ 結果を確認
- 第2段階: 「その構成の『はじめに』の部分を500文字で書いて」
- ↓ 結果を確認
- 第3段階: 「同じトーンで次の見出しも書いて」
原則4:例を示す
- 例を示さない: 「親しみやすい文章で」
- 例を示す: 「『僕も最初はそう思ったんです』『一緒に頑張りましょう!』のような親しみやすい文章で」
原則5:制約を明確にする
文字数や構成、スタイルなどを具体的に指定することで、AIの迷いをなくせます。
- 文字数: 「300文字程度で」
- 構成: 「見出し3つと各200文字の説明で」
- スタイル: 「です・ます調で」
- 対象読者: 「AI初心者向けに専門用語は使わず」
AIとの対話を改善する実践テクニック

プロンプトの原則を踏まえた上で、さらに会話の質を上げるためのテクニックを紹介します。
テクニック1:「AIに確認させる」
AIは、時として私たちの指示を誤って解釈することがあります。
意図と違う作業を進めてしまう前に、AIに「あなたの理解は正しいか?」と確認させることで、手戻りを大幅に減らせます。
具体的なプロンプト例
「この指示で何をするか、簡潔に説明してください。」
「私の依頼内容を、要点をまとめて箇条書きで確認してください。」
テクニック2:「段階的詳細化」
一度に完璧な答えを求めず、大きな枠組みから始めて、段階的に詳細を詰めていく方法です。
まるで、AIとキャッチボールをするように少しずつ完成形に近づけていきます。
具体的なプロンプト例
Step 1: 大枠を決める → 「40代向けのAI活用ブログ記事の構成案を考えて」
Step 2: 詳細を詰める → 「その構成の『はじめに』の部分を500文字で書いて」
Step 3: 調整する → 「もう少し親しみやすい表現に変えて」
テクニック3:「フィードバックループ」
AIの回答が期待通りでなかった場合でも、ただやり直すのではなく、具体的なフィードバックを返すことで、AIは学習し、次の回答の質が上がります。
具体的なプロンプト例
- 指示を出す
- 結果を評価する
- 改善点を具体的に伝える
「もう少し具体的な事例を入れてもらえますか?『ChatGPTで議事録作成時間が半分になった』のような具体例を2つほど」 - 修正を依頼する
業種別・用途別の効果的なプロンプト思考法

AIに指示を出すとき、実は「どんな仕事で使うか」によってプロンプトの書き方は変わってきます。
あなたの仕事に合わせてAIの得意なことを引き出しましょう。
ここでは、あなたの仕事でAIをどう活用できるか、そのための思考法を具体的な例で見ていきましょう。
コンサルタント・士業の方
重視すること:信頼性と専門性
思考法:AIに「情報の正確さ」や「論理的な構成」を求めます。
プロンプト例
「〇〇の統計データに基づいて、日本の平均年収の変動について500文字で解説してください。」
「中小企業庁の発表を引用し、中小企業の経営課題に関する報告書を専門家向けにまとめてください。」
クリエイター・デザイナーの方
重視すること:創造性と個性
思考法:AIに「感覚的なイメージ」や「ムード」を伝えます。
プロンプト例
「午後の柔らかな木漏れ日をイメージした、淡い水彩画風のイラストを生成してください。ノスタルジックな雰囲気を加えてください。」
「アメリカンコミック風で、スーパーヒーローが街を守るシーンを描いてください。」「1980年代のピクセルアート風で、レトロゲームのキャラクターを生成してください。」
教育・研修関係の方
重視すること:分かりやすさと段階的な学習
思考法:AIに「学習者のレベル」や「ステップ」を明確に指定します。
プロンプト例
「小学校5年生でも理解できるよう、日本の歴史を年表形式で分かりやすく説明してください。」
「AI活用の基礎を学ぶための、3ステップの学習ロードマップを考えてください。」
AI理解度をチェック!セルフ診断
最後に、今日学んだことがどれだけ身についたか、一緒にチェックしてみましょう!
実践編
□ 曖昧な表現を具体的な表現に言い換えられる
□ 5W1Hを意識してプロンプトを作れる
□ 段階的に指示を出すことができる
□ AIからの回答を評価し、改善点を具体的に伝えられる
□ 用途に応じてプロンプトの書き方を変えられる
□ 期待値を適切に設定できる
6個中の得点で判断:
- 5-6個: AIマスター!自信を持って、周りの人にもコツを教えてあげましょう!
- 3-4個: 上級者です。あと一歩でAIマスター!さらなる実践で効率化を目指しましょう。
- 1-2個: 基本はOKです。今日からAIとの対話を楽しみながら、少しずつ実践を重ねてみましょう。
- 0個: まずはこの記事をもう一度読んで、基本理解から始めてみましょう。応援しています!
まとめ|「5つの原則」や「3つのテクニック」を試そう

いかがでしたか?
AIとの効果的な対話は、私たちの曖昧な思いを、AIが理解しやすい具体的な言葉に「翻訳」すること。
それは、今日ご紹介した「5つの原則」や「3つのテクニック」を試すことで、誰にでも身につけられるスキルです。
難しく聞こえるかもしれませんが、心配いりません。
まずはあなたの仕事や趣味でAIをどう活用したいか、一つだけ目標を決めて、このページを参考にプロンプトを書いてみてください。
AIに分かりやすく伝えることを意識すると、自然と相手の立場に立って具体的に話す習慣が身につきます。
それは、人とのコミュニケーションにも役立つ、素晴らしいトレーニングになるんです。
さあ、AIとの対話を楽しんでみましょう!
▶プロンプトの基礎中の基礎はこちらからどうぞ!
【理論編】の記事はこちらからどうぞ! → [AIは「推測」で答えていた?!なぜAIに意図が伝わらないのか、その理由を徹底解説]